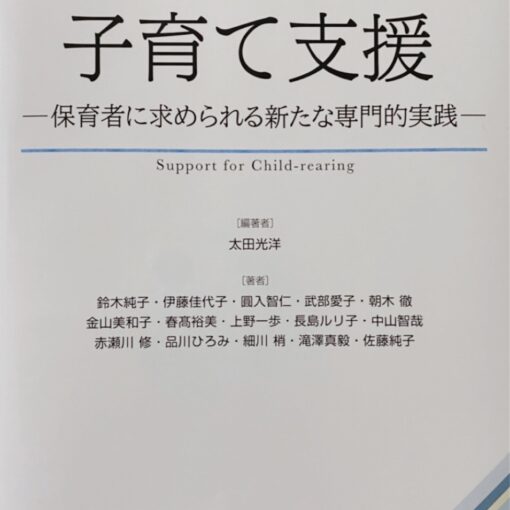子どもたちにも変化が表れ始めた
【子どもたちと継続的に関わる意味】
今年度4年目となる、小値賀町の小中学生への授業がスタートしました。
小値賀町の小中学校の先生たちは、だいたい3年で異動になるため、私が4年前に初めて授業をさせていただいた時にいらっしゃった先生たちは、ほぼ異動されました。
子どもたちの心身の健康、成長には、コーチングコミュニケーションが有効なのではないかと、興味、関心を持って最初に関わっくださった先生たちはいらっしゃらないのですが、
こうして4年目を迎えられている理由の一つに、子どもたちの反応、成長が結果として表れ始めたことがあげられるのかもしれません。
すべての言動のもとになる
『自分とどんな話をしているか(自己対話)』
というテーマを持ち、子どもたちと作り上げる時間は、とにかく、
『安心して自分を表現できる場』
になることを目指しています。
親、先生、親戚、地域の方、先輩、後輩、年上、年下、そういう立場や肩書き、また、同級生の中での立ち位置などを意識すると、ときに自分が望んでいない自己対話が進んでしまうことがあります。
それは決して悪いことではありません。
自分なりに悩みながら、葛藤しながら、ときには無意識に、今できる精一杯の自己対話なんだと思います。
ただ、それが固定化されてしまうと、自分を表現する幅や深さも、きっとある程度のところで固定されて、
『自分はこうなんだ』
というものを自分で決めてしまい、ときに、自分を表現できないもどかしさや、苦しさに向き合わないといけなくなります。
それももちろん悪いことではないし、経験として成長につながることもあります。
ただ、変わらないものとして決めつけたり、諦めや失望に発展させたりしないようにと、私はこの授業を届けてきました。
4年目ともなると、子どもたちも私との時間がどんな時間なのか知っています。
『楽しみにしてたー!』
『思ったことなんでも書いていいんだよね!』
という言葉は、たくさんもらえるようにもなりました。
日ごろ、そんなに気にすることなく、スルーしていた思いも、振り返ってみると、
『あれ、あのときけっこう嫌だったんだな』
と気づくことがあります。
それを自分自身も、第三者のコーチも、とにかく受け止める、そしてさらにクラスの仲間や先生にも受け止めてもらう、
そこから、自分をどうあたたかく応援していこうか、コーチと一緒に考えていく。
こういう機会の繰り返しで、
自分も人も大切にできる考えが自然と身についていくんだなと、子どもたちの声、先生たちの声を聞きながら感じられるようになってきました。
今回、先生の中のお一人が言葉を綴ってくださいました。
————————-
生徒たちの『心の対話』は、驚くほど深く、豊かでした。生徒のリアルな思いがあふれていました。『自分の思い』と『仲間の思い』その違いを知ることで、また自分と対話し始める。生徒たちが立ち止まり、考える姿を見ながらまた考える…この時間は、ただの授業ではなく、『生きる力』を育む時間だったのだと思いました。
————————-
先生たちとお話をしていて、『学校』『教育』って大切だし、尊いし、意義深いものだと今までとは違う視点から感じるものがありました。
子どもの心身ともに健全な成長のために通ってほしい道がそこには本来あって、その中で自分自身が成長していくきっかけを自分でつかんでいくことができる場であるべきなんだろうなと考えることもできました。
1人の人間の人生を支えるものや、人生の広がりや彩りを感じるためのものを、共につかむことができる仕事でもあるのかと思うと、やっぱり先生ってかっこいいし、魅力いっぱいな職業だなとまた再確認しました。
先生たちの入れ替わりが頻繁な地域ではありますが、先生たちにもご理解いただきながら、同じ方向を向いて、一緒に子どもたちに関わらせていただき、
【子どもが自分の選択を積み重ねて、自分という人間を精一杯生きる】
きっかけとして、お手伝いが少しでもできたらなと思っているので、引き続きよろしくお願いいたします。